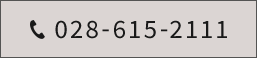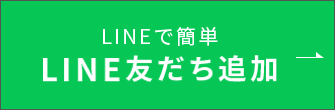アレルギー性結膜炎とは
 アレルギー性結膜炎とは、アレルギー反応で結膜に炎症が起こる疾患です。
アレルギー性結膜炎とは、アレルギー反応で結膜に炎症が起こる疾患です。
私たちの身体には、ウイルスや細菌などの病原体が体内へ入り込んだ時、それにくっついて体外へ追い出そうとする物質が生成されます。この物質が「抗体」です。
抗体は一度作られると、同じ抗原に再び出会った時、すぐに反応して除去してくれます。この働きは「抗原抗体反応」と呼ばれています。
しかし、この免疫システムは時々間違えて、本来身体に害のない物質(花粉や食べ物など)にも抗体を作ってしまいます。また、抗体の量が必要以上に多くなったり、自分自身の細胞を攻撃したりすることもあります。
これらの間違いによって、本来なら無害であるはずの物質(アレルゲン)が体内に入ると、過剰な反応が起こります。これがアレルギー反応です。アレルギー性結膜炎も、このアレルギー反応の一種です。
アレルギー性結膜炎の種類
花粉症(季節性アレルギー性結膜炎)
 花粉にアレルギー反応を起こす疾患です。花粉が鼻や目に触れた結果、体内にある肥満細胞(マスト細胞)が過剰に反応し、ヒスタミンという物質を放出してしまうことで起こります。
花粉にアレルギー反応を起こす疾患です。花粉が鼻や目に触れた結果、体内にある肥満細胞(マスト細胞)が過剰に反応し、ヒスタミンという物質を放出してしまうことで起こります。
花粉症を起こす植物としては、スギ(春)やイネ(夏)、ブタクサ(秋)などが挙げられます。花粉そのものには、毒性が含まれていません。
花粉症の方は、特定の花粉が飛散する季節になると、毎年同じような症状に悩まされます。そのため花粉症は、季節性アレルギー性結膜炎とも言われています。花粉症の方の70%が季節性アレルギー性鼻炎を併発するとも指摘されています。
通年性アレルギー性結膜炎
 ダニやハウスダスト、動物の抜け毛、フケ、カビなどのような、季節を問わずどの時期でも存在しているアレルゲンによって発症する疾患です。発症するメカニズムや症状は、花粉症と同じです。1年中、症状が慢性的に続くのを特徴としています。
ダニやハウスダスト、動物の抜け毛、フケ、カビなどのような、季節を問わずどの時期でも存在しているアレルゲンによって発症する疾患です。発症するメカニズムや症状は、花粉症と同じです。1年中、症状が慢性的に続くのを特徴としています。
現代の住宅は密閉されており、冷暖房も完備されていますが、これはダニにとって快適な環境です。定期的に掃除をしてホコリやダニを減らしたり、窓を開けて空気を入れ替えたりすることが大切です。
春季カタル
春季カタルは、アレルギー性結膜炎の中でも重度なもので、慢性的に症状が続きます。「春季」は「若年者」を意味する言葉で、特に小学生の男子に多い傾向があります。
最近では、アトピー性皮膚炎と併発するケースが増えており、20代の大人にも強い症状が見られるようになっています。
発症すると目がとてもかゆくなり、結膜に石垣のようなできものが生じます。黒目(角膜)の部分にも傷がつき、光を見ると眩しく感じることもあります。炎症がひどくなると、角膜が白く濁ったり、濁った部分の上皮が落ちて「角膜びらん」「角膜潰瘍」になったりする可能性もあります。
巨大乳頭結膜炎
コンタクトレンズのタンパク汚れに対する、アレルギー反応によって発症する疾患です。発症すると、上瞼の裏に大きなポツポツとした、結膜乳頭による隆起が沢山発生したり、炎症が起こったりします。目の異物感や目やに、視界のくもりなどの症状が起こり、重症化するとコンタクトレンズが上の方にずれやすくなります。
アレルギー性結膜炎の治療
 かゆみなどの症状を抑える作用を持っている、目薬がよく使われます。具体的に言いますと、ケミカルメディエータ遊離抑制薬、抗ヒスタミン薬などのような薬で症状を落ち着かせます。症状が重い場合は、ステロイドや免疫抑制剤を使って治します。
かゆみなどの症状を抑える作用を持っている、目薬がよく使われます。具体的に言いますと、ケミカルメディエータ遊離抑制薬、抗ヒスタミン薬などのような薬で症状を落ち着かせます。症状が重い場合は、ステロイドや免疫抑制剤を使って治します。
抗アレルギー点眼薬
メディエーター遊離抑制薬
アレルギーの原因となるヒスタミンなどの物質(メディエーター)を、肥満細胞から出させないようにする目薬です
抗ヒスタミン薬
アレルギーの症状を引き起こすヒスタミンが、血管や神経の受容体(ヒスタミンH1受容体)にくっつかないようにする目薬です。
ステロイド薬
上記の目薬では効かない場合や、かゆみがひどい場合に使われる目薬です。
先述した目薬よりも効果はすぐに発揮されますが、副作用もあるので注意して使わなければなりません。
免疫抑制点眼薬
春季カタルの治療に使われる目薬です。上記に述べた目薬の効果が実感できなかった時に使います。
アレルギー性結膜炎の初期療法
花粉症の方の場合、花粉が飛び始める時期の2週間前から、もしくは症状が少し出てきたタイミングで抗アレルギー点眼薬を使うことをお勧めします。この初期療法を行うと、飛散シーズン中でも症状の軽減に期待できます。
花粉症が毎年ひどい方は、症状が目立たない段階からご相談ください。
かゆみを和らげる方法
「かゆいから」と思って目をこすると、アレルギー症状を起こすヒスタミンなどのメディエーターが増えやすくなります。目の腫れや結膜の水ぶくれなど、重い症状が起こりやすくなるので、こするのは我慢しましょう。
かゆみを和らげる方法
- 冷たいタオルなどを目に当てて冷やす
- 保冷剤をタオルにくるんで、目に当てる
- 点眼薬を使う前には、人工涙液や点眼型洗眼薬などでアレルゲンを洗い流す
日常生活で気を付けた方が良いこと
アレルギー性結膜炎を防ぐには、アレルギーの原因物質(アレルゲン)に極力触れない生活を送る必要があります。
花粉情報
 ニュースやネットを活用して、花粉情報をチェックしましょう。
ニュースやネットを活用して、花粉情報をチェックしましょう。
花粉が多い日は外出を避けるか、マスク・花粉用眼鏡を着用すると良いでしょう。マスクは隙間がないようにしっかりと装着しましょう。また、眼鏡は花粉が入りにくいゴーグルタイプがお勧めです。
外出から帰った際は、衣服や髪の毛についた花粉を払い落としましょう。手洗いやうがいも忘れずに行ってください。
室内では空気清浄機を使い、洗濯物は室内で干しましょう。体調を崩すと症状が重くなりやすいので、規則正しい生活とバランスの良い食事で免疫力を高めましょう。
室内環境の整備
アレルゲンとの接触を減らすため、室内環境の整備を心がけましょう。
- 室内の清掃:ホコリが溜まりやすい箇所は特に気を付ける。室内環境に考慮しながら、掃除機やぞうきんなどを使い分ける。
- 寝具:屋外で天日干しする。布団乾燥機を使う。掃除機でダニを吸い取る。
- 通気と除湿
- ペット:アレルゲン検査でペットの毛やダニが原因と言われた場合は、室内でのペット飼育を極力避けてください。
コンタクトレンズのケア
 コンタクトレンズを使用されている場合は、レンズの汚れに気を付けなくてはなりません。目の潤いを維持させる涙の中には、タンパク質や脂質などが入っています。それらがコンタクトレンズに付いたままでいると、レンズが汚れてしまいます。
コンタクトレンズを使用されている場合は、レンズの汚れに気を付けなくてはなりません。目の潤いを維持させる涙の中には、タンパク質や脂質などが入っています。それらがコンタクトレンズに付いたままでいると、レンズが汚れてしまいます。
吸着性のあるタンパク質や脂質に、空気中に漂う花粉や微生物がくっついてしまうと、アレルギー性結膜炎の症状が起こりやすくなります。
また、目を頻繁にこすると、目の粘膜に傷が付いて感染リスクが高まってしまいます。症状がさらにひどくなる恐れがあるので、コンタクトレンズを使っている方は気を付けて洗浄しましょう。
コンタクトレンズが汚れやすい方は、ワンデータイプなどのように、レンズ汚れを気にせずに使えるものに変更することもお勧めです。清潔なレンズが毎日使用できるので、症状の軽減にも期待できます。